よそものから見た、きつね火まつり
こんにちは!編集メンバーの蛯谷です。
私は現在大学院生で、FCLでは研究のお手伝いをさせていただいています。
今回は、9月末に飛騨のきつね火祭りに参加してきた感想を、外部の目線からつらつらと書いてみようかと思います。
きつね火まつりとはなんぞや?!と思った方、『飛騨市ファンクラブときつね火まつりの進化』の記事も合わせてご覧ください!
きつね火まつりとは?
きつね火まつりの詳細は別記事にお譲りするので、ここでは簡単にご紹介。
きつね火まつりは、平成2年に飛騨古川の地元商工会青年部が、町おこしの一環として始めたものです。飛騨古川で古くから伝わる、「きつねの嫁入り物語」を現代風にアレンジしたもので、当日は「きつねの嫁入り行列」が、町路を厳かに進み、最後に婚礼の儀が行われます。行列は、本物の新郎新婦を乗せた台車を中心に様々な道具や楽器を持ちながらゆっくりと飛騨の街を歩きます。メインの行列は夜ですが、昨年から昼行列も行われるようになりました。最後の儀式が行われる祭り会館では、朝から屋台も立ち並び、地元の人や観光客で賑わいます。
当日のスケジュール
(0. 受付・着替え・メイク)
1. お披露目行列
2. 花嫁・花婿 瀬戸川散策
3. 祝いの儀
4. 嫁入り行列
5. 結びの儀
祭りは上記のようなスケジュールで開催されました。私は、昼行列に参加し、夜の行列と結びの儀の最後を観覧しました。
当日は11時に公民館に集まり、ボランティアの方に着付けとメイクをしてもらいます。

この白丁という昔ながらの狩衣は、着るのがすごく難しく、少なくとも私は補助がないと綺麗に着られませんでした。メイクは、写真のようなきつねを模したもので、人によってその人に合うようにメイクの仕方をマイナーチェンジしてくださいました。
着替えとメイクの後、午後からはお披露目行列に参加しました。昼行列は、古川小学校から祭り会館までの約600mの道をゆっくりと歩きます。提灯や嫁入り道具を持ち運ぶ人たちと、巫女鈴や拍子木を鳴らす人たちなどがおり、賑やかな行列です。また、昼行列の参加者は地元の人たちに加えて飛騨市ファンクラブに加入している人の参加枠があり、今回私たちはその枠で行列に加えていただきました。

そして、夜にはより人数の多くなった夜行列が開催されます。夜行列は、松明に火をつけて持ち歩いていたり、太鼓の厳かな音が鳴っていたりして、昼とはまた違う雰囲気でした。祭りを見に来ている人たちは、一旦行列が目の前を通り過ぎても、行列のルートを地図で確認しながら、次に通る場所に先回りして行列を待ちます。

最後は、まつり会館の中央ステージで結びの儀が行われます。儀式の最後には地元の銘酒も振舞われ、盃を持っている人は何杯でもお代わりすることができます。(大盤振る舞い!)
参加した感想
私は富山県出身なのですが、上京してからはもちろん地元にいる間も、こうした祭りに参加することは滅多になかったので、凄く貴重で面白い経験になったと思っています。色々と思ったことはあるのですが、その中でも特に感じたことを挙げるとすると、
「よそ者」でも一緒に楽しめる雰囲気
なんといっても、きつね火まつりの(いい意味で)独特な、オープンな雰囲気。 正直、なんだかんだ言っても祭りは地元のものだし、特に飛騨古川の場合は三大奇祭にも数えられるほどの古川祭りへの思い入れが半端ない!というイメージがあったので、部外者である自分が参加しても大丈夫なのか、と前日まで緊張していました。
でも、そんな心配は杞憂。準備段階から衣装の着付けやメイクのボランティアの方はすごく優しくご対応していただけて気がほぐれました。祭り会場では誰にでもきつねのメイクをしてくださるコーナーがあります。こういうちょっとした心遣いがあることで、誰でも祭りに溶け込むことができるようになるのかな、と思いました。
また先述した通り、きつね火まつりは地元の人たちが中心になり、毎年アイディアを出し合って形にしていくお祭りです。それもあってか、飛騨に住む人と飛騨を訪れた人が一体となって毎年独特の世界観を作り上げるスタンスを感じました。
語彙力が足りなくてうまく伝えられませんが、「地元ならではの祭り、観光客は外野」ではなく、「一緒に今年のお祭りを作り上げよう!」というような雰囲気を感じました。
地元文化を知ろうとするきっかけ
私は、今年の8月に古川に住む知り合いからきつね火まつりのことをお聞きし、そこで初めて存在を知りました。仮装して行列を歩くお祭り、とだけ聞いたので、なんだかよくわからないなと思って調べてみると、「きつねの嫁入り行列を模したものである」という特色を発見しました。そもそも「きつねの嫁入り」という言葉は知っているもののそれがどんな話なのか、きつねの嫁入りと飛騨古川との関係性に関してはよく知らず、純粋に疑問に思ったので更に調べてみました。
ご存知の方ばかりかもしれませんが、「きつねの嫁入り」とは、夜の闇に提灯のような怪火が連なる現象のことで、日本各地で伝承されているもの。飛騨古川にはこの行列を見た人は、五穀豊穣・家内安全・商売繁盛のご利益があるとされているそうです。
これまで自分は祭りを目的に旅行に行くことはなかったし、どこかの祭りに行くとしても、その由来や儀式の意味について考えたことはありませんでした。祭りなのに「何かをまつる」という意識がなく、ただ浴衣を着て屋台を回ることに満足していたからかなと思います。こうして地域行事に参加することで、その街の文化や歴史を少しでも考える良いきっかけになると感じました。
最後に
きつね火まつりのような、地元の人で作り上げているお祭りは、全国各地で開かれているのではないかと思いますが、あまり参加したことはないし、そういった情報は普段なかなか手に入らない気がします。でも、お祭りは地域文化を知ったり、身近に感じたりするとても良いきっかけになるなと実感できたので、またこうした地域のお祭りには積極的に参加してみたいなと思いました。

最後に、いつか結婚できた暁にはきつね火まつりの花嫁に応募したい…!








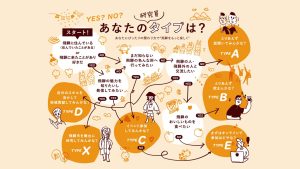
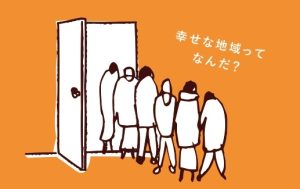

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] […]